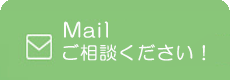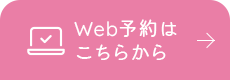回答
乳癌と食べ物の関係について、大豆・イソフラボンや乳製品がメディアでも取り上げられていますが、現時点で医学的にも統計学的にも分かっていることは4つだけです。
①肥満は確実に乳癌のリスクになる
②アルコールは確実に乳癌のリスクになり、摂取量が増えるほどリスクも高まる。
③大豆やイソフラボンは、乳癌の発症リスクを減らす可能性があるが、まだ研究段階。
④乳製品は、乳癌の発症リスクを減らす可能性があるが、まだ研究段階。
解説
肥満とアルコールは医学的にも統計学的にも因果関係が証明済みですので、この2つを避けることは乳癌の予防にも直結します。アルコールは、ビールなら中ジョッキ1杯、ワインならグラス2杯までであればリスクにはならないとされています。
イソフラボンとは、大豆などのマメ科の植物に微量含まれている成分です。女性ホルモン(エストロゲン)と似た構造をしているため、エストロゲンをエサにして増殖するタイプの乳癌のリスクになると考えられていましたが、乳癌の治療で使われるホルモン剤とも似た構造も含まれているため、乳癌の予防効果が期待されています。
日本を含むアジア人を対象とした研究では、大豆製品を多く摂取している人の方が乳癌の発症リスクが低いという統計が報告されていますので、十分に期待してよいと思いますが、具体的に「どのような大豆製品をどれくらい摂取すればよいのか?」までは分かっていません。現在進行中の大規模な統計の結果が出てくるまでは、あくまでも可能性止まりです。
*医学的な統計にはとても時間がかかります。大豆を多く摂取する人とそうでない人を数万人ずつ集めて、その食生活を10年~20年続けてもらって初めて答が出ます。
それから、イソフラボンをサブリメントとして摂取することでの乳癌に対する効果は検証されていません。逆に乳癌のリスクを上げてしまう可能性もありますし、現時点では過剰摂取(厚生労働省の勧める1日30mg未満を超える量)の安全性すらも不明です。イソフラボンを摂取する場合は、必ず大豆食品から摂取してください。
乳製品に関しては、これまでは乳癌の発症リスクを上げるとされていましたが、大規模な統計結果が揃った結果、2019年以降の日本乳癌学会のガイドラインでは「乳製品の摂取により乳癌の発症リスクが減る可能性がある」と示されています。
欧米人でよく見られますが、乳製品を好んで摂取する方の中には肥満の方の割合が多いため、乳製品は乳癌のリスクの1つと考えられていましたが、研究が進むにつれて「乳製品そのものはリスクにはなっていない。むしろ、乳製品全般を多く摂取している人は、そうでない人に比べて乳癌の発症リスクが低くなっている」ことが分かってきました。
ただし、分かっているのは乳製品全般という大まかなものであり、「どの乳製品が良いのか?」や「牛乳はどうなのか?」までは分かっていないのが現状です。乳製品には人が健康に生きていくために必要な栄養素が豊富に含まれているため、幅広い乳製品を、肥満にならない程度に食事の範囲内で摂取することが大事です。
その他、市販のサプリメントや健康食品に関しては、摂取しても乳癌の発症リスクは低くならないことが証明されています。特定のビタミン類、食物繊維や脂肪酸に関しては、乳癌との関連性は何も分かっていません。食生活や生活習慣の中で乳癌のリスクとの関連性が研究・報告されているものを以下にまとめていますので、ご参照ください。
| 要因 | 乳癌の発症リスク |
| 肥満 | 確実にリスクが上がる *閉経前であれば確実視まではされていない研究もあります。しかし、閉経するまでは肥満で、閉経後に急に標準体重に戻すことは現実的ではありませんので、肥満は避けましょう。 |
| アルコール | 確実にリスクが上がる |
| 大豆食品 | リスクが下がる可能性がある |
| イソフラボンのサプリメント | 不明(安全性も不明) |
| 乳製品 | リスクが下がる可能性がある |
| 健康食品やサプリメント | リスクが下がることはない |
| 喫煙 | 確実にリスクが上がる |
| 運動 | 確実にリスクが下がる |
| ストレス | 不明 |
| 性格 | リスクとは関連なし |
| 糖尿病 | 確実にリスクが上がる |
参照)
日本乳癌学会 患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版
https://jbcs.xsrv.jp/guideline/p2023/gindex/100-2/q62/
日本乳癌学会 乳癌診療ガイドライン2022年版
https://jbcs.xsrv.jp/guideline/2022/e_index/s4/